
妊娠中の方は、母体と赤ちゃんの健康のために必ず妊婦健診を受けなくてはいけません。
妊婦健診では、週数ごとに血液検査が必要になります。血液検査でどんな病気のチェックをするのか、何回検査があるのか、気になっている人も多いのではないでしょうか。
このコラムでは、妊婦健診で血液検査を行うタイミングや検査項目などについて詳しく紹介します。血液検査に向けて備えておきたい人は、ぜひ最後までお読みください。
妊婦健診での血液検査の目的
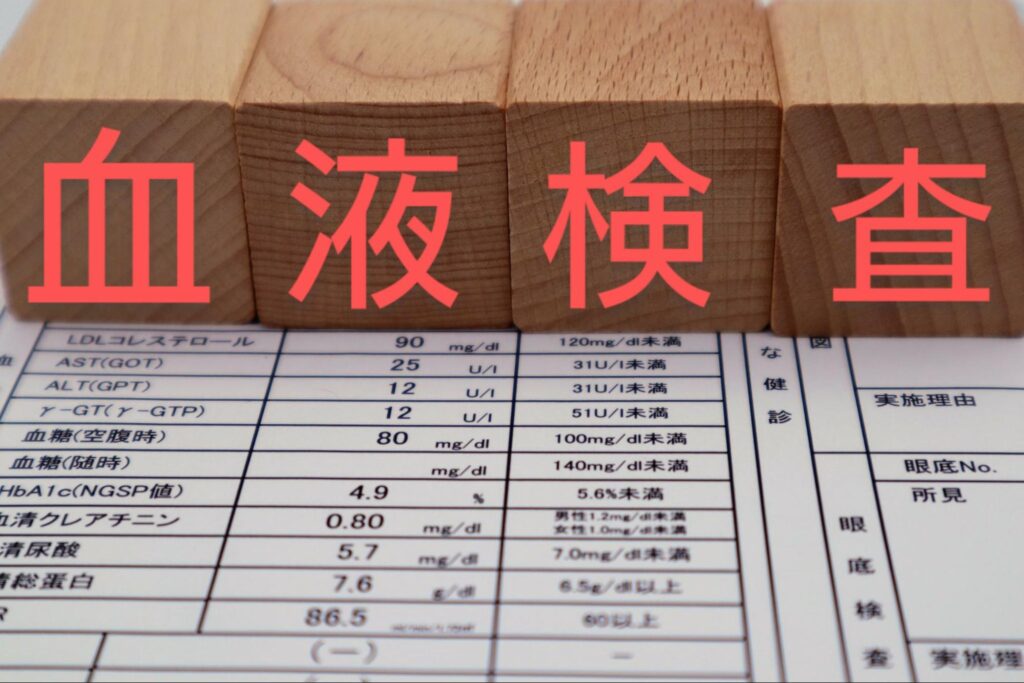
まずは、妊婦健診で血液検査を行う目的について見ていきましょう。
血液検査の目的
妊婦健診で行う血液検査の目的は、妊娠が順調であるかの確認や感染症などの病気の早期発見や予防を目的としています。
病気を放っておいたまま妊娠週数が進むと、胎児にも病気が移ったり、出産後に胎児に異常が見られたりする可能性があります。
そのため、妊婦健診ではお母さんと赤ちゃんの健康のために、血液検査を行うのです。
万が一妊婦健診の血液検査で異常が見つかった場合は、妊婦健診の間隔を短くして経過観察を行ったり、ワクチンの接種や入院したりして対応します。
病気や異常が見つかった場合には、医師の指示を必ず確認して治療を受けましょう。
妊婦の血液は胎児にとって大切
妊婦の血液は、胎児にとって非常に有効な役割をしています。
普段から血液は、各器官に酸素や栄養を届けたり、不必要な老廃物を排出したりする役割を担っています。
妊娠するとそれ以外にも、胎盤を通して赤ちゃんに酸素や栄養を送る役割を担うのです。また、赤ちゃんも老廃物を出すため、それを排出する役割もしています。
妊婦の血液は、赤ちゃんの体を作るために大切なものです。妊婦さんの血液に異常があると、胎児にも影響を及ぼす可能性があります。
そのため、血液検査で妊婦さんの血液をチェックすることが必要なのです。
妊婦健診のスケジュール

妊婦健診のスケジュールと、健診で行う内容について紹介します。妊婦健診の頻度と検査内容について一例を紹介します。
病院によってスケジュールは若干異なりますが、おおまかな流れを把握しておきましょう。以下で、スマイルレディースクリニックの妊婦健診のスケジュールを紹介します。
| 妊娠週数 | 健診内容 | 検査 |
| 妊娠5〜7週 (2週間毎) | ・子宮内に妊娠しているか、胎児心拍が確認できるか | ・超音波検査 |
| 妊娠8〜9週 (2週間毎) | ・胎児の大きさ、心拍の有無などから分娩予定日を決定 | ・超音波検査 |
| 妊娠10〜12週 (2週間毎) | ・母親の血圧、尿蛋白・貧血有無、血液型 ・胎児の発育、大きさ | ・初期血液検査 (貧血/梅毒/血糖/血液型/HIV/B型肝炎/C型肝炎/風疹抗体価/ATL抗体/不規則抗体/HbA1c)・子宮頸がん検査 ・膣分泌物細菌培養 ・クラミジアPCR |
| 妊娠13〜19週 (4週間毎) | ・母親の血圧、尿蛋白の有無 ・胎児の発育、大きさ | ・子宮頸管長測定 |
| 妊娠20〜24週 (4週間毎) | ・母親の血圧、尿蛋白有無 ・胎児の発育、大きさ | |
| 妊娠25〜27週 (2週間毎) | ・母親の血圧、尿蛋白の有無 ・胎児の発育、大きさ | ・50g糖負荷試験 ・貧血検査 |
| 妊娠28〜30週 (2週間毎) | ・母親の血圧、尿蛋白・貧血有無 ・胎児の発育、大きさ | ・精密超音波検査 |
| 妊娠31〜32週 (2週間毎) | ・母親の血圧、尿蛋白有無 ・胎児の発育、大きさ |
スマイルレディースクリニックでは、出産予定の病院・施設から許可がある場合、妊娠34週頃までは当院で妊婦健診を受けていただくことが可能です。
妊婦健診の血液検査はいつ?3つのタイミング

妊婦健診の血液検査は、妊娠初期・中期・後期と3つのタイミングで行います。それぞれの検査内容について、詳しく見ていきましょう。
妊娠初期(妊娠15週まで)
妊娠初期に検査する内容について紹介します。
血液一般検査
血算は、血液に含まれる白血球、赤血球、血小板などの数値を調べる検査です。妊婦健診に限らず、血液検査の際によく行われます。
この検査を行うことで赤血球数や白血球数、血小板の異常などを調べることが可能です。
また、貧血のチェックも行います。妊娠中の貧血と判断される基準は、ヘモグロビン10 g/dL未満です。
貧血の場合は、鉄剤などを服用して鉄分を補います。白血球の数が多い場合は、炎症性疾患や感染症の疑いがあるため、再検査を行います。
血糖
妊婦健診では、妊娠糖尿病のチェックのため血糖値も計測します。
妊娠糖尿病は、妊娠前に糖尿病の傾向が見られなかった方でもかかりやすい病気です。
妊娠糖尿病になると胎児が合併症を引き起こす可能性があり、巨大児、新生児低血糖、発育遅延などの症状が起こる可能性があります。
血液型
妊婦健診では、お母さんの血液型も検査します。A型・B型などのタイプを調べるだけでなく、「Rh血液型」や「不規則抗体」など赤血球のタイプも調べます。
これは、出産時に大量出血してした場合に輸血する可能性があるためと、血液型不適合妊娠のリスクを避けるためです。
血液型不適合妊娠とは、母親と胎児の血液型のタイプが異なり、母親に赤血球に対する抗体ができることをいいます。
血液型不適合妊娠になるとお母さんの体内で赤ちゃんを敵とみなして胎児の赤血球を攻撃してしまい、貧血や浮腫、流産・早産・死産などのリスクが高くなるのです。
この場合は、子宮内胎児輸血や出産後に交換輸血を行うなどの対処が必要です。
甲状腺機能
甲状腺機能の検査は、血中甲状腺刺激ホルモン(TSH)と血中遊離サイロキシン(FT4)を測定します。
バセドウ病や橋本病などの甲状腺機能異常症などがチェック可能です。
甲状腺機能に異常がある場合には、流産・早産・妊娠中毒症のリスクが高くなります。
妊娠中に甲状腺疾患が分かった場合は、薬を服用して甲状腺ホルモンの分泌量をコントロールするなどの治療を行い、赤ちゃんの成長や発達への影響を抑えられるようにします。
感染症の検査
妊娠中に感染症にかかっていると、胎児への感染や先天性の異常を引き起こす可能性があります。
もしも感染が疑われる場合は、より詳しい検査が必要です。感染症検査でチェックする病気について、それぞれ紹介します。
【HIV】
HIV検査は、エイズの原因になるHIV(ヒト免疫不全ウイルス)に感染していないかを確認する検査です。
感染がわかって治療を行えば、赤ちゃんへの感染のリスクを抑えることも可能です。
感染に気が付かずに出産した場合の母子感染率は約30%ですが、治療を行った場合の感染率は0.5%にまで減少します。
【B型・C型肝炎抗体】
B型肝炎・C型肝炎は、肝臓の病気です。治療せずに放っておくと、慢性肝炎、肝硬変、肝臓がんなどになる可能性があります。
肝臓は沈黙の臓器と呼ばれるため、病気に気が付かずに進行してしまう可能性もあります。
検査が陽性の場合は母子感染のリスクがあります。
【トキソプラズマ】
トキソプラズマは、動物が持っている寄生虫の一種で人にも感染する恐れがあります。
大人であれば症状が出ることは少ないですが、妊娠中に感染すると胎児にも感染する可能性があり、発達の遅れや脳性麻痺、流産・死産などの恐れがあります。
ペットの世話やガーデニング、生肉の摂取などで感染する可能性があるため、妊娠生活中は気をつけるようにしましょう。
【風疹抗体】
妊婦健診での風疹抗体検査では、風疹の抗体価を調べます。
予防接種を受けていない人はもちろん、以前に予防接種を受けていても抗体の量が少なくなっている場合もあるので、抗体の量を確認します。
風疹は、ウイルス感染によって起こる急性ウイルス性発疹症です。主に発熱、発疹などの症状が起こります。
妊娠20週までの妊婦が風疹にかかると、胎児に影響が起こり、目や心臓の異常、聴覚への影響などを引き起こす可能性があります。
【梅毒】
梅毒は病原菌の感染による性感染症です。
梅毒に感染すると、最初は発疹やしこりができ、進行すると微熱や倦怠感、リンパ腫の腫れなど全身症状が出ます。
妊娠中期(妊娠24〜35週)
妊娠中期の血液検査でチェックする項目について見ていきましょう。
血液一般検査
妊娠中期でも赤血球や白血球、血小板などの数や性質を調査します。主に貧血や出血時の血液の止まりやすさを調べます。
血糖・50g糖負荷試験
妊娠中期を過ぎると体重が増えやすくなり、血糖も高くなりがちです。妊娠初期よりも妊娠糖尿病のリスクが高くなるため、血糖値を調べます。
また、「50g糖負荷試験」と呼ばれる、検査用の飲み物を飲んで血糖値の上昇具合を見る検査も行います。
血糖値が140mg/dl以上の場合は妊娠糖尿病の疑いがあると判断し、さらに詳しい検査を行います。
HTLV-1抗体検査
HTLV-1は成人T細胞白血病、リンパ腫などを引き起こす可能性のあるウイルスです。お母さんがHTLV-1ウイルスを持っていると、母乳によって赤ちゃんに感染する可能性があります。
HTLV-1検査は妊娠30週までに行う検査のため、妊娠初期の血液検査で調べることもあります。
妊娠後期(妊娠36週〜出産まで)
最後に、妊娠後期の血液検査でチェックする項目を見ていきましょう。
なお、スマイルレディースクリニックでは、出産予定の病院・施設から許可がある場合、妊娠34週目頃までの妊婦健診を実施しています。
妊娠後期の検査に関しては、出産先の病院で受診するようにしてください。
血液一般検査
妊娠中期でも赤血球や白血球、血小板などの数や性質を調査します。主に貧血や出血時の血液の止まりやすさを調べます。
血液検査前の食事は控える

妊婦健診で行う血液検査の前は、基本的に食事を控えましょう。
病院によっては前日の21時以降食事禁止、当日のみ食事禁止などが定められています。血液検査を行う前の検査で、血液検査を行う旨と注意事項について説明があるので、必ず守りましょう。
採血前に食事をしてしまうと、血糖値や中性脂肪の数値が上がり、診断に影響する場合があります。
また、砂糖が多く入った甘い飲み物も血糖値に影響を及ぼすため、控えるようにしてください。正しい検査結果を出すためにも、病院からの注意を必ず守って血液検査を受けるようにしましょう。
妊婦健診にかかる費用
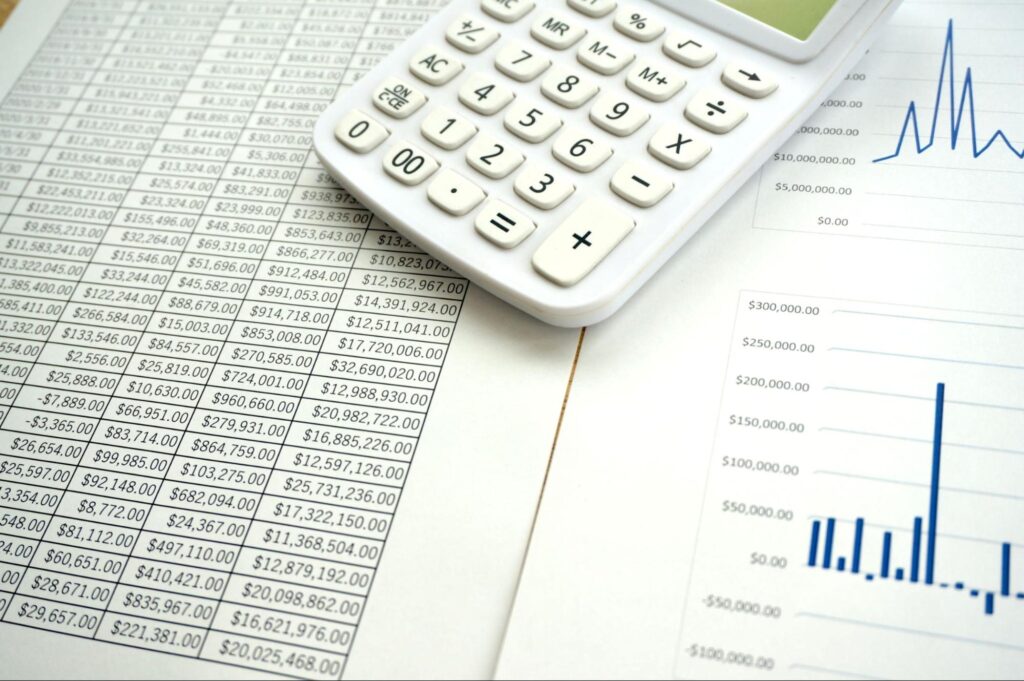
妊婦健診にかかる費用や、費用を抑える方法について詳しく見ていきましょう。
妊婦健診の費用
妊婦健診にかかる費用は、トータルで10〜15万円です。
体重計測や血圧測定などの基本検査のみを行う場合は1回3,000〜7,000円程度、血液検査などの週数によって必要な検査が加わる場合は、1〜2万円程度費用が必要になります。
血液検査を行う日は事前に伝えられるので、費用を忘れないように持参しましょう。
補助券で費用を抑えられる
妊婦健診の費用は全額自己負担ですが、各自治体から発行される補助券を使うことで、費用を抑えられます。
補助券には割引される金額が記載されているため、妊婦健診の金額によって提出するようにしましょう。
補助券は、お住まいの市区町村で妊娠届けを提出すると、母子手帳と一緒にもらうことができます。補助券の金額は自治体ごとに異なるため、お住まいの地域で確認してみましょう。
再検査
血液検査で異常が見つかった場合は、再検査が必要です。
再検査にかかる費用は自費になります。ただし、保険が適応になる場合があるため、病院で確認してみましょう。
まとめ
妊婦健診の血液検査は、妊娠初期・中期・後期の3回行います。主に感染症にかかっていないか、出産にリスクはないかなどの観点で検査を行います。
血液検査までに食事をすると結果に影響する可能性があるため、病院で言われた注意を守って受診するようにしてください。
スマイルレディースクリニックでは、妊娠5週〜34週までの妊婦健診を行っています。近隣の分娩施設の紹介や、里帰り前までの妊婦健診も行っていますので、ぜひお気軽にお越しください。
